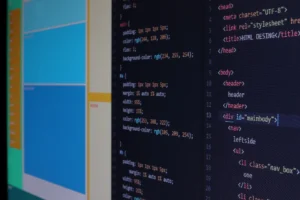ホームページを作ろうと考えたとき、現在ではWix(ウィックス)やSTUDIO(スタジオ)のような高機能な自作ツールがたくさんあり、「自分で安く作れるなら、その方がいいのでは?」と考える方は非常に多いです。
これまで100以上のサイト制作に携わり、その中でリニューアル前に“素人の方が自作した”ホームページも数多く拝見してきました。
その経験から断言できるのは、「自作した結果、貴重な時間とコストを無駄にし、結局プロに依頼し直す」ケースが非常に多いということです。
それ以上に深刻なのは、中途半端なサイトを公開してしまったことで、かえって会社や事業への「信頼性」を失っているケースです。
この記事では、なぜ自作が失敗しやすいのか(デメリット)と、プロに依頼する真のメリットを、多くの事例を見てきたプロの視点で徹底比較します。
- プロが実際に見てきた「自作ホームページの失敗あるある」
- 自作の5つの重大なデメリット
- 制作会社に依頼する本当のメリット
- 自作と依頼のコストや品質の比較
- あなたが「自作向き」か「依頼すべき」かの判断基準
なぜ「自作しない方がいい」のか? よくある自作失敗例とデメリット
私たちがリニューアルのご相談を受ける際、自作されたサイトには共通する「問題点」があります。
- 【信頼性】一瞬で「素人感」が伝わり、信頼を失う
- 【セキュリティ】「保護されていない通信」で、ユーザーが離脱
- 【成果】「集客」と「売上」につながらない
- 【時間】想像を絶する「時間的コスト」と「学習コスト」
- 【機会損失】「安く済ませた」つもりが、最も高い買い物に
【信頼性】一瞬で「素人感」が伝わり、信頼を失う
ビジネスにおいて、ホームページは「会社の顔」です。しかし、自作サイトには下記のような「素人感」が出やすく、訪問者に不安を与えてしまいます。
- ウォーターマーク(透かし文字)入りの画像無料の素材サイトから取得した「SAMPLE」という透かし文字が入った画像をそのまま使っている。
- デフォルトドメインを使っている独自ドメイン(〇〇.comなど)を取得せず、「〇〇.sakura.ne.jp」のようなサーバー会社のドメインをそのまま使っている。これでは「仮のサイトかな?」と思われてしまいます。
- ファビコンが未設定ブラウザのタブに表示される小さなアイコン(ファビコン)が設定されておらず、ツールのデフォルトアイコンのままになっている。
- デザインやレイアウトの崩れスマホで見たときに、文字が画面からはみ出したり、画像が不自然に拡大されたりする。
これらが当てはまると、訪問者は「この会社、大丈夫かな?」と不安になり、すぐに離脱してしまいます。
【セキュリティ】「保護されていない通信」で、ユーザーが離脱
これは非常に多く、かつ深刻な問題です。
- SSLに対応できていない
SSLとは、サイトの通信を暗号化する仕組みです。URLが「http://」のまま(正しくは「https://」)だと、ブラウザに「保護されていない通信」と警告が表示されます。
Googleも、SSL化(常時HTTPS化)を推奨しており、警告の出るサイトは訪問者に強い不安感を与えます。個人情報を入力する「お問い合わせフォーム」がSSL化されていないのは論外です。
参照:Google Chrome のセキュリティ インジケーターについて – Google Chrome ヘルプ
【成果】「集客」と「売上」につながらない
ホームページを作る目的は「集客」や「売上アップ」のはずです。しかし、自作サイトの多くは「作ること」がゴールになっており、成果につながりません。
- 検索に表示されない(SEO対策ができていない)プロは「検索ユーザーがどんな言葉で探すか」を想定してページを作りますが、自作ではその視点が抜け落ちがちです。結果、Googleで検索しても誰にも見つけてもらえません。
- CV(成果)につながる構成になっていない訪問者が「欲しい情報」にたどり着けず、「使いにくい」と感じて離脱します。どこに「お問い合わせ」ボタンがあるか分かりにくく、効果的なライティング(文章)もできていないため、サービスや商品の魅力が伝わりません。
【時間】想像を絶する「時間的コスト」と「学習コスト」
自作ツールは「簡単」と謳っていますが、それはあくまで「基本的な操作」です。
- プロ並みのデザインにしようとすると、ツールの学習に数週間かかる。
- デザインの調整、スマホ対応、エラー対処に追われ、本業が圧迫される。
経営者や担当者の貴重な「時間(人件費)」を、不慣れなサイト制作に費やすのは、結果的に最も高いコストとなります。
【機会損失】「安く済ませた」つもりが、最も高い買い物に
中途半端なサイトを公開した結果、
- 成果が出ない
- 信頼も失う
- 結局プロに作り直しを依頼する
こうなると、自作にかかった時間と費用(ツールの月額費など)が全て無駄になります。さらに、公開までに半年かかれば、その間のビジネスチャンスも全て失っています(機会損失)。
【比較】制作会社に依頼する本当のメリット
自作のデメリットは、そのまま「制作会社に依頼するメリット」になります。
- 【成果】「集客」と「売上」から逆算した戦略的設計
- 【信頼】企業の「信頼」を獲得するプロ品質
- 【時間】「本業に集中できる」という最大の価値
- 【安心】公開後の「保守・運用」という安心感
【成果】「集客」と「売上」から逆算した戦略的設計
プロは「カッコいいデザイン」を作るだけが仕事ではありません。
- SEOとマーケティング視点で、訪問者を成果(CV=お問い合わせ・購入)に導く「売れる構成」を設計します。
- 誰に・何を・どう伝えるか、という戦略から考えるため、成果が出るスピードが全く違います。
【信頼】企業の「信頼」を獲得するプロ品質
自作のデメリットで挙げたような「素人感」は一切ありません。
- 独自ドメインの取得、SSL対応、ファビコン設定などは「当たり前」として対応。
- 企業のブランド価値を高め、訪問者に「信頼できる会社だ」という印象を与えるデザインを提供します。
【時間】「本業に集中できる」という最大の価値
これが経営者にとって最大のメリットかもしれません。
- 面倒な作業はすべて丸投げできます。
- 経営者や担当者は、サイト制作に時間を取られることなく、売上を作る「本業」にリソースを集中できます。
【安心】公開後の「保守・運用」という安心感
サイトは「作って終わり」ではありません。
- 公開後のセキュリティ対策、サーバー管理、トラブル対応まで一任できます。
- 法改正(例:特定商取引法に基づく表記)や、新しい情報への更新作業もスムーズです。
比較表で一目瞭然!自作 vs 制作会社
自作とプロへの依頼を、項目別に比較してみましょう。
| 比較項目 | ホームページ自作 | 制作会社への依頼 |
| 初期費用 | 安い(0円~数万円) | 高い(数十万~) |
| 時間的コスト | 非常に高い(学習・作業時間) | 非常に低い(打合せのみ) |
| 集客力 (SEO) | 難しい(専門知識が必須) | ◎(戦略的に設計) |
| デザイン品質 | △(素人感・信頼性欠如) | ◎(プロ品質・信頼性◎) |
| サポート | 無し(すべて自己責任) | ◎(保守・運用サポート) |
| トータルコスト | (失敗すると)結果的に高い | (成果が出れば)費用対効果が高い |
あなたはどっち?判断基準のチェックリスト
ここまで読んで、「自分はどちらを選ぶべきか」を判断する基準をご提案します。
⬜︎「自作」でも良いケース(例外)
- 目的が「名刺代わり」で、集客を一切期待しない。
- Web制作の学習自体が目的である(趣味など)。
- 時間は無制限にあるが、予算は1円もない。
⬜︎「プロに依頼」すべきケース
- ホームページから問い合わせや売上を増やしたい。
- 本業に集中したい。
- 競合他社に見劣りしない、信頼性のあるサイトが欲しい。
- SEOやセキュリティについて考えるのが面倒だ。
- 自作に挑戦したが、挫折してしまった。
成果の出るホームページは「投資」です
ホームページは「作ること」が目的ではなく、「成果を出すこと」が目的です。
もしあなたが、ビジネスを成長させるための「集客」や「企業の信頼性向上」を望むなら、「自作」は遠回りになる可能性が非常に高いです。
制作会社クオリティを、適正コストでご提供します
「とはいえ、制作会社は費用が高すぎる…」とご不安かもしれません。
ご安心ください。弊社は([例:少数精鋭である、制作プロセスを効率化している等、御社の強み])により、大手制作会社のクオリティを保ちながら、コストを抑えた制作が可能です。
もちろん、公開後の保守や運用のサポートもお任せください。
「自作で挑戦してみたけど、うまくいかない」
「自社の場合、どれくらいの費用で何ができるのか知りたい」
まずは御社の現状を「無料相談」でお聞かせください。費用対効果の高いご提案をいたします。