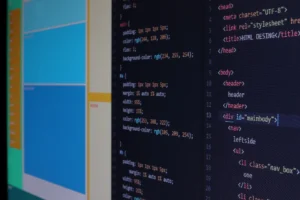・「企業の採用力を強化したいが、採用サイトは今の企業サイトのままで良いのだろうか?」
・「わざわざコストと手間をかけて、採用サイトを独立させるメリットは本当にある?」
企業の採用担当者や経営者の方と商談をしていると、このような悩みを非常によく伺います。
これまで100以上のWebサイト制作に携わってきたWebディレクターの私が解説します。 結論から言えば、「採用に本気で力を入れるなら、採用サイトは企業サイトから独立させるべき」です。
しかし、すべての企業に当てはまるわけではありません。コストをかけて失敗しないためには、明確な「判断の根拠」が必要です。
この記事では、私が実際にクライアントへ提案した事例を基に、採用サイトを独立させるべき理由と、あなたの会社がどちらを選ぶべきかの判断基準をプロの視点で詳しく解説します。
なぜ、採用サイトと企業サイトを分ける必要があるのか?
本題に入る前に、大前提として「なぜ」分けるのかを整理します。 それは、2つのサイトでは「ターゲット(訪問者)」と「最終目的」が根本的に異なるからです。
- 企業サイト(コーポレートサイト)
- ターゲット: 顧客、取引先、投資家
- 目的: 製品・サービスのPR、企業の信頼性アピール、IR情報の発信(=信用の獲得)
- 採用サイト
- ターゲット: 求職者(新卒・中途)、転職潜在層
- 目的: 「ここで働きたい」と思わせる魅力付け、リアルな社風の伝達(=入社意欲の醸成)
顧客は「信頼できる会社か」を見ていますが、求職者は「自分が輝ける職場か」を見ています。この視点の違いが、サイトを分けるべき最大の理由です。
【提案事例】急成長フィットネススタジオになぜ「サイト分離」を提案したか
先日、まさにこの問題に直面したクライアント(急速に店舗拡大を進めるフィットネススタジオ様)の事例をご紹介します。
当初のご依頼は、「企業サイト内にある採用ページをリニューアルしたい」というものでした。しかし、ヒアリングを進めるうちに採用サイトとして分けて作成することを提案しました。
私がそう判断した根拠は、以下の4点です。
- 採用に関するコンテンツ(情報量)が膨大だった
- 希望するイメージが企業サイトとかけ離れていた
- サイト全体の情報設計が複雑化するのを避けたかった
- 将来のメンテナンス性(運用効率)を高めたかった
1. 採用に関するコンテンツ(情報量)が膨大だった
募集要項だけではなく、「充実した研修制度」「多彩なキャリアパス」「店舗ごとの社員インタビュー」など、求職者に伝えたい魅力的な情報が山のようにありました。これらを企業サイトの1ページに詰め込むと情報が渋滞し、本当に伝えたいことが伝わりません。
2. 希望するイメージが企業サイトとかけ離れていた
企業サイトは、顧客(会員様)向けに「清潔感・信頼感」を重視したクリーンでスタイリッシュなデザインでした。 しかし、採用でターゲットとなる人材は「情熱的でエネルギッシュな若手」。採用ページでは「熱い想いが伝わる、感情に訴えるデザイン」を希望されており、デザインの方向性が真逆でした。
3. サイト全体の情報設計が複雑化するのを避けたかった
既存の企業サイトも、店舗拡大に伴い「新店舗情報」「新サービス」など、顧客向けの情報を随時追加している状況でした。そこに方向性の違う大量の採用コンテンツが加わると、サイト構造が複雑化します。 結果として、顧客はサービスを探しにくく、求職者は採用情報にたどり着けないという、誰にとっても使いにくいサイトになる危険性がありました。
4. 将来のメンテナンス性(運用効率)を高めたかった
これが長期的に見て非常に重要です。もしサイトを分離しておけば、将来「企業サイトをフルリニューアルしよう」となった場合でも、採用サイトは影響を受けずにそのまま運用し続けられます。逆も然りです。
採用サイトを分ける「5つのメリット」
先の事例からも分かる通り、採用サイトを独立させると明確なメリットが生まれます。
・求職者に最適化された情報を深く届けられる
・採用ブランディング(魅力付け)を強化できる
・入社後のミスマッチを防ぎ、定着率向上に繋がる
・運用効率が上がり、サイトが「育つ
・長期的な採用コストを削減できる
1. 求職者に最適化された情報を深く届けられる
企業サイトではノイズになりがちな「社員の1日のスケジュール」「リアルなインタビュー動画」「詳細なキャリアパス」なども、採用サイトなら主役として存分に掲載できます。
2. 採用ブランディング(魅力付け)を強化できる
事例のように、企業サイトのトーン&マナーに縛られません。求職者の心に響く「エモい」デザインや、「情熱的」といったキャッチコピーを使い、自社で働く魅力をダイレクトに訴求できます。
3. 入社後のミスマッチを防ぎ、定着率向上に繋がる
「楽しそう」といった良い面だけでなく、仕事の厳しさやリアルな姿も深く伝えることで、求職者の過度な期待を補正できます。入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップを減らし、早期離職の防止に繋がります。
4. 運用効率が上がり、サイトが「育つ」
事例の4点目でも触れた通り、サイトが分離していれば、採用担当者は採用活動の動きに合わせて、企業サイト側の都合を気にせずスピーディーに情報を更新・追加できます。将来のリニューアルも容易です。
5. 長期的な採用コストを削減できる
自社の採用サイトが育てば、求人媒体への依存度を下げることが可能です。自社サイト経由での直接応募が増えれば、将来的に求人広告費や人材紹介手数料を大幅に削減できる可能性があります。
デメリットと「SEOに関する最重要の注意点」
もちろん、メリットばかりではありません。デメリットもあります。
1. 制作コストと運用リソースの発生
当然ながら、サイトを一つ新しく作るための初期費用(数十万〜)がかかります。また、情報更新のための工数(人件費)や、サーバー代などの維持費も別途必要です。
2. ブランドイメージの乖離リスク
企業サイトと採用サイトのデザインやメッセージがかけ離れすぎると、「結局、この会社はどっちが本当なの?」と求職者を混乱させ、企業ブランドの統一性が失われる可能性があります。
そして、サイトを分ける際に技術的に最も注意すべき点がSEOです。
1. 絶対に避けるべきなのは「別ドメイン」
例えば、企業サイトが example.com なのに、採用サイトを example-recruit.com のような全く新しいドメインで取得することです。これでは、企業サイトが長年蓄積してきた「ドメインパワー(SEO上の評価)」を一切引き継げず、検索結果で上位表示されにくくなります。
2. 最適解は「サブディレクトリ」
example.com/recruit/ のように、企業サイトのドメイン配下にフォルダ(ディレクトリ)を作って設置します。 この形式なら、親ドメイン(example.com)のSEO評価を継承しつつ、採用コンテンツを独立して管理することができます。
(※recruit.example.com という「サブドメイン」形式もありますが、SEO評価の引き継ぎ効果はサブディレクトリよりやや弱いとされるため、私はサブディレクトリを推奨しています)
採用サイトを分ける判断根拠
では、ここまでの情報を踏まえ、あなたの会社がどちらを選ぶべきか、具体的な判断基準をまとめます。
▼「分ける」ことをお勧めする企業
- 採用に本気で、継続的に活動している。
- 急速に事業拡大しており、採用人数が多い。
- 募集職種や勤務地が複数あり、掲載すべき情報量が多い。
- 企業サイトと採用サイトで伝えたいイメージが明確に異なる。
- 求人媒体経由での応募者とのミスマッチに課題を感じている。
▼「一体型」のまま(または簡易的な分離)でも良い企業
- 採用が欠員補充などスポット的で、頻度が低い。
- 採用にかけられる予算や人的リソースが極端に限られている。
- まずは企業情報(理念や事業内容)を深く知ってもらうことが最優先。
まとめ
私が100以上のサイト制作を担当してきた経験から言えるのは、「採用への投資=未来への投資」だということです。
採用サイトを独立させることは、単なるWeb制作ではなく、「自社にマッチした優秀な人材」を獲得するための戦略的な投資です。
初期コストはかかりますが、それによって「採用のミスマッチが減る」「採用ブランディングが確立する」「長期的な採用コストが下がる」というメリットは、そのコストを上回る価値をもたらします。
まずは、「自社が求職者に本当に伝えたい魅力は何か」「どれくらいの情報量があるか」を整理することから始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたの会社の採用活動を成功に導くための一助となれば幸いです。